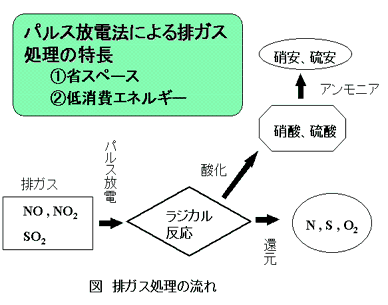現在我々が直面している地球環境問題の一つに,酸性雨の問題が挙げられます.酸性雨の原因物質は化石燃料の燃焼により生じる窒素酸化物(NOXなど),硫黄酸化物(SO2など)です.
我が国においては火力発電所等,固定発生源の排ガスに関しては脱硫・脱硝技術は確立されおり,移動発生源である自動車のうち,ガソリンエンジンに対しては三元触媒によりNOX,SO2は優良なレベルに抑制されています.しかし,ディーゼル車に対しては有効な技術が確立されていません.それは,以下のような制約からです.ガソリン車においても最近注目のリーンバーンエンジン,直噴エンジンは酸素濃度が大きいため三元触媒が有効に機能しません.つまり,高酸素濃度でつかえるNOX処理技術の確立が待ち望まれているわけです.
- 処理装置が車載可能である大きさ,重量であること
- エネルギー効率(出力の10%以下)
- 排ガス中の酸素濃度が高いため三元触媒が有効に機能しない
- 黒煙の原因であるすすの処理の問題
そこで新しいNOXの処理方法として有望であるパルス放電による排ガス処理法についての研究をしています.
パルス放電とは何か?
針-平板型電極,ワイヤ-平板型電極,同軸円筒型電極などの電極間に電圧をかけたとき著しい不平等電界ができる放電管に,直流高電圧を徐々に印加していくと,ある電圧で高圧側の電極の周りで局所的な絶縁破壊がおき,光り始める.このときの放電をコロナ放電(部分放電の一種)という.ちなみにさらに電圧を上げていくと雷のように強い光の筋が電極間を短絡する.この放電をアーク放電(または火花放電)という.パルス放電はコロナ放電が起きる状況で印加する電圧をパルス化にしたもので,パルスの立ち上がり時間数10ns,パルス幅1μs程度の極めて短いパルスである.
コロナ放電では高圧電極の周りだけが光るが,パルス放電は高圧電極から光の筋がアース側電極に伸びる(短絡はしない).このため,同じ電圧でも広い領域をプラズマ化でき,これまでのコロナ放電による排ガス処理よりエネルギー効率の面で有利である.
| 同軸円筒型の放電管における
パルス放電の発光の様子 (外径 37mm 中心電極径 0.5mm) (印加電圧 16.8kV 窒素ガス:2.0 L/min) |
排ガス処理の流れ
放電によりできたプラズマ(ここでいうプラズマは電界により電子のみ加速され,イオンはほぼ動かない”冷たいプラズマ”または,”非平衡プラズマ”である.)により出来るラジカル(反応性が高い粒子),例えばN,OHがNOと以下のように反応してNOが除去される.分光解析HNO3はアンモニアと中和させて硝酸アンモニウムとして回収される.
- 還元;NO+N→N2+O
- 酸化;NO+OH→NO2+H
- NO2+OH→HNO3
これまでに研究されてきたコロナ放電による排ガス処理では,酸化反応が主でした.本研究では自動車への車載を考慮し,還元反応が主であるような排ガス処理を目指しています.そこで,放電管内の反応を知ることで,還元反応への糸口を探ろうというわけです.そのための手法として,放電光の分光解析を行っています.
放電管内で起きている反応の定量的なことは,反応時間が非常に短いため余り研究さていません.そこで本研究は放電光を分光解析する事でなどを知ることが目的です.
- 生成するラジカルの寿命
- 放電容器内の高速電子の空間分布
- ガス組成の排ガス処理への影響
以上が研究テーマで概略です.なおこの研究は工業技術院 電子技術総合研究所 放電環境応用ラボと共同で研究しております.
'98 10/20 update.